生み出すものには勝てない。
毎日早朝に目覚め、昨晩に決めたその日の題材についてどのような解説を書こうか考える日々を送っているうちに、おぼろげに分かってきたことがあります。
やっぱり、生み出す人は偉大だ。
この一言に尽きます。
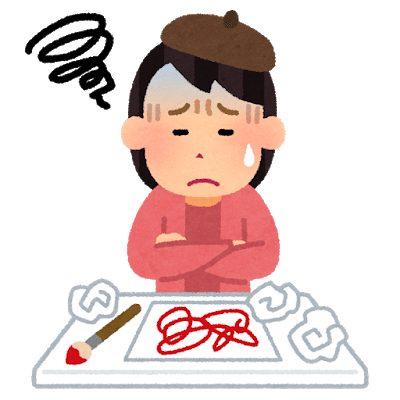
どんなに御大層な学歴を持ち、様々な出版社から「解説欄」の執筆を依頼されるような敏腕の評論家であっても、やはり自ら苦しんで生み出す作家たちに比べれば足下にも及ばないのではないのかと。
最近、そんなことを考えておりまして。
実は、これだけたくさんの小説を読みあさっている僕ですから、自分で小説を書いてみよう、という挑戦をしたことは何度もありました。
今日は、ほんのちょいとだけ自分で書いてみたものをちょっとここに載せてみたいと思います。
彼はJRの高架線の下が好きだ。そこを通ると、鼠色に塗りたくられた壁にどこぞのヤンキーが書いたABCを眺めるために、必ず足を止めるくせがあった。それは筆で描いたような黒い文字に白い縁取りで、うねりだらけの文体はさながら養殖場にいるウナギを壁に貼り付けた様であり、雨の日などはちょうどウナギが壁の上をのたうち回ったかのようにきらきら濡れた。彼がいわゆる仕事というものに通い始めて十数年たっていたが、そのABCはいつも彼を同じ場所で迎えつづけていた。彼もまた、仕事帰りに高架線の下を通るときは喜んで挨拶をするのだ。幼少時からの知り合いに会うことは、私たちの心に強い安心感を与えてくれることがある。彼が感じていたのはまさしくそれであった。灰色の壁に描かれた煩雑な落書きはもちろん、高架下にはあらゆる不潔なものがあった。格子蓋にはいたるところにガムがこびりつき、ついぞ見たこともないような文字が書かれているペットボトルが油の浮く汚水とともに電車の振動と共鳴している。壁際には毛の禿げかかった野良猫が自分の子供と一緒に道路脇に投げ捨てられたカップ麺の空容器を嘗め回している。しかし彼は壁のABCやらペットボトルやら、ひいては壁際で陰険な目つきをしている野良猫まで、いとおしむように眺めるのを日課にしていた。中でもお気に入りは電車の無粋な振動とともにゆらゆらうごめく水色のペットボトルである。中に入っている深緑色の液体が、外の世界と一緒に震えるのである。彼はその何かを訴えるような紋様を眺め、その訴えを想像しては楽しむのであった。(オリジナル)
ううむ。。
実際自分の文章を読み返すたびに、比べることさえおこがましいのですが、やっぱり僕が好きで読んでいるような作家たちの文章には到底及ばないな、というため息が口から漏れ出てきます。
何が足りないのか?
しいて言えば、「どれだけ苦しんで生み出したのか」ということではないでしょうか。
芸術創作には必ず苦しみがつきまといます。それは我が子を産む母親の陣痛の苦しみの如く、小説家にとっては一字一句が、音楽家にとっては一節のジェネラルパウゼに至るまで、それらを考え出すのにはひどい苦しみを感じなければならない。
かのドストエフスキーも、有名な「カラマーゾフの兄弟」を脱稿するのにひどく苦労したみたいです。彼の新妻で速記者のアンナ・ドストエフスキーに励まされながらなんとか書き上げた、というお話まで残っております。
「カラマーゾフの兄弟」を書き上げた後、彼はあっという間に力尽きて死んでしまいました。
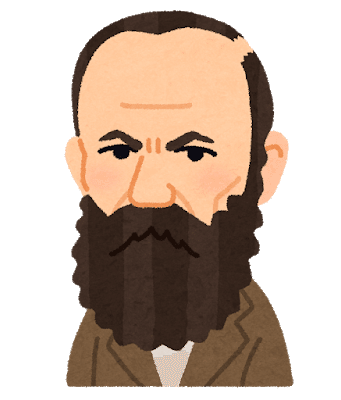
芸術家は自分の作品の細部にまでこだわります。まさしく一つ一つのディテールがその作品の全体をなす大切な要素であり、1ミリも気を抜くわけにはいきません。画家が目の前のモデルの少女の瞳を描くのにどれほど苦心したことでしょう?芥川が自らの小説に出て来る登場人物のセリフを考え出すのに、どれほどの苦痛を味わったでしょう?
僕には苦しみが足りない。どうせ趣味だから~などと適当なことを考えて、さっきのような文章を適当につらつらと書きなぐっているだけ。
これでは誰の心も捉えることができません。
その作品を生み出すのに芸術家が割いたエネルギーが大きければ大きいほど、その作品は多くの人の心を動かします。
さらに追い打ちをかける事実があります。
芸術家は芸術家であると同時に、サラリーマンでもあります。つまり、生活のために自分の描いたものを売らなければならないのです。
これが何を意味するか。
彼らは生み出さなければならない。かつ、自分の好きなものばかりを生み出すわけにはいかない。必ずみんなに読んでもらえるような、みんながお金を出して買ってくれるようなものを生み出さなければならない。
売れている芸術家は、こんな途方もないくらい難しいタスクにたった独りで取り組んでいます。
これにはとてつもない労力がかかるのではないでしょうか。到底自分には真似することはできません。じっさい、さっき掲げたような短い文章を書くのでさえ、なかなか進まなくてできないくらいです・・・
自ら苦しんで生み出すものには誰も勝てない。たとえどれだけ彼が評価されてなかったとしても。
たった1か月半ですが、とても大切なことを学ばせてもらったような気がしています。
今日もお読みいただきありがとうございます。皆様の一日が素敵なものになりますように。
変わってるって、強さのことだ。
ーーー「きみ、変わってるね。」と言われたら、どう思いますか。
特に日本では「変わった人」というのはネガティブな意味で使われることが多いような気がします。変わってるやつ、馴染めないやつ。社会不適合者、みたいな。
しかし、文学は教えてくれます。「変わった人」こそ強いんだ。他にはない強みを持っているからこそ、「変わった人」はいつも孤独なんだ。
ヘルマン・ヘッセ「デミアン」の中で、旧約聖書のカインとアベルの物語について語られる部分を抜粋してお届けします。ーーー
下の記事の続きです↓
ヘッセ「デミアン」より。カインとアベルの物語。
あの忌々しいフランツ・クロオマアの事件から数か月たった。
最近になって新入生が訪れた。マックス・デミアンという少年だった。
どことなく風変わりな生徒で、見た目よりもずっと老けている感じがした。彼は自分が「少年」である、という印象を誰にも与えなかった。仲間どうしの遊びにも、けんかにも加わらなかったし、同級生の誰とも深く関わろうとはしなかった。ただ、彼が教師たちに対して、自信満々のきっぱりとした態度をとるのが同級生たちを喜ばせていた。
ある日のことだ。僕らは旧約聖書を学んでいた。有名な「カイン」と「アベル」の物語である。それはこういうお話だった。
2人は各々の貢ぎ物を神ヤハウェに捧げる。カインは収穫物を、アベルは肥えた羊の子を捧げたが、ヤハウェはアベルの供物に目を留めカインの供物は目を留めなかった。これを恨んだカインはその後、野原にアベルを誘い殺害する。その後、ヤハウェにアベルの行方を問われたカインは「知りません。私は弟の番人なのですか?」と答えた。これが人間のついた最初の嘘とされている。しかし、大地に流されたアベルの血はヤハウェに向かって彼の死を訴えた。カインはこの罪により、エデンの東にあるノドの地に追放されたという。この時ヤハウェは、もはやカインが耕作を行っても作物は収穫出来なくなる事を伝えた。また、追放された土地の者たちに殺されることを恐れたカインに対し、ヤハウェは彼を殺す者には七倍の復讐があることを伝え、カインには誰にも殺されないためのカインの刻印をしたという。(Wikipediaより引用)
その日の帰り道。マックス・デミアンは僕に話しかけてきた。今でも忘れられない。彼が僕に与えた第一印象はあまりにも衝撃的だった。
彼はどう考えてもイカれているような驚くべきことを言ってのけたのだ。
「つまり、僕は思うんだがね。このカインの物語は、全く別の解釈もできるんだ。確かに、正しい話であるには違いないさ。でも、先生がみるのとは違った見方をすることもできるんだし、そうしたほうが、大抵は意味が深くなるんだぜ。たとえば、あのカインも、そのひたいにある刻印も、僕たちの聞かされている説明の通りでは物足りない感じがするじゃないか。けんかで弟を殴り殺すなんて、実際ありそうなことだし、そいつがあとで後悔してへこたれてしまうことも、ありうることさ。しかしそいつがその臆病のご褒美に、とくに勲章を授けられて、その勲章が彼を保護したうえに他のみんなを怖がらせる、というのはずいぶん妙な話だと思わないか?」
「じっさい簡単なお話だったのさ。この物語の発端になっているのは、刻印だったんだよ。一人の男がいた。そいつには、みんなを怖がらせるようなものがその顔についていた。みんなはその男に手出しをする勇気がなかった。その刻印は、目に見えてわかりやすいものじゃなくてもいい。それはどことなく薄気味悪い雰囲気のことだったのさ。つまり、彼には視線の中にみんなが見慣れているより以上の、才知と勇気とが宿っている、ということなのさ。この男は強かったんだ。この男を見るとみんなはしり込みしたんだ。」
「さて、彼以外の一般の人々というものは、いつだって自分に都合の良いもの、自分を正しいと認めてくれるものを望むんだ。みんなはカインと彼の子孫を怖がった。カインとその子孫たちは皆、例の刻印を持っていたのさ。でも、一般の人はそれをありのままに説明せず、まったく真逆の物として説明しようとした。つまり、この刻印のついているやつらは気味が悪い、という話を受け継いできたんだ。じっさい、気味が悪かったのかもしれないね。そうすることによって、カインとその子孫たちのような強い連中にケチな復讐をしよう、今までに自分たちが受けた恐怖の埋め合わせをしようとしたんだ。わかるかい。」

「わかるよ!じゃ、つまりカインはちっとも悪い奴じゃなかったってことだね。聖書に書いてあること嘘っぱちなんだ。」僕は言った。
「いや、そうでもあり、そうでもなしだ。こういう古い物語はどこまでも真実なんだけどね、いつも正しく書き記されているとは限らないのさ。つまり、僕の言いたいことはね。カインという奴は素敵な野郎だったんだけど、あまりにも魅力的すぎてみんなに怖がられたばっかりに、こんな物語をくっつけられてしまった、ということなんだよ。この物語は、なんのことはない、世間でよくあるうわさ話の一つなのさ。しかしカインとその子孫が、他のみんなとはどこか違ってて、刻印を持っていた、という部分だけはやっぱり真実だったんだね...」
(続く)
「変わり者」って、強さのことだ ーー解説ーー
こいつはすごい。
僕も初めてこの部分を読んだときには衝撃を受けました。
聖書の「カインとアベル」の話は、非常に分かりやすい物語です。しかし、デミアンの言う通り、神が弟を殺した罪人にわざわざ刻印をつけて保護をした、というのはどことなく奇妙な話です。もしデミアンの言う通りで、カインという奴は本当に素敵な野郎だったとしたら。このお話は、私たちに一つの大きな教訓を与えてくれます。
現代でも、本当にいろんな方がいて、いろんな人生を歩まれています。それでもほとんどの方は、社会の中で何とか自分の立ち位置を見つけて、働きながら暮らさなければ生きていけません。
その中で、「人間関係」というのはダントツで一番の悩みの種です。
もしかしたらこの記事を読んでくださっている方の中にも、こうしためんどくさい人間関係に煩わされている方がいらっしゃるかもしれません。

自分はなんとなくまわりに好かれないな・・・
自分では普通にしているつもりなのに、なんとなくみんなが気さくに接してくれない、私、ハブられているのかな・・・
こんなふうに思うこともきっとあると思います。
そんな時、この「カイン」と「アベル」のお話を思い出してほしいのです。そして、堂々と自分にたいしてこう言い張っちゃいましょう。
「わたしは、カインの子孫なんだ」と。
どことなく周りの雰囲気に馴染めないのは、あなたが周りの人たちよりも優れた一面を持っているから。そして、周りの人たちはそんなあなたの優れた部分が怖くて仕方がないから、あなたをハブってしまう。
おそらくこれは事実です。なぜなら、歴史上で何かを変えることのできた強い人間はたいてい変わり者で嫌われ者だった、というお話まであるくらいですから。
自分が嫌われているな、と思ったら、自分は周りよりも優れているから嫉妬されているんだな、と思っちゃいましょう。そうすれば、めんどくさくて仕方が無いような人間関係の悩みも少しだけ軽くなるような気がしてきませんか。
わざわざ自分の中にある優れた部分を捻じ曲げてまで、周りに合わせる必要はまったくありません。うまく衝突をしないように身をかわしながら、それでも自分を変えようとはせずに、堂々とそのままでいればいいのです。
そんな強いメッセージを旧約聖書の中から読み取った、このマックス・デミアンという少年はいったいどんな人物なのでしょうか。また明日から、一緒に追っていきたいと思います。
思春期の少年、苦しく美しい心の中。
ーーー中学校の国語の授業で、誰もが深く印象に残っている、あの「クジャクヤママユ」の話。あの物語を書いた作家が、ヘルマン・ヘッセである。
「クジャクヤママユ」を盗んだあの主人公のように、不安定な思春期の真っただ中、誰しも一度は「悪」に触れたことがあるのではないか。スーパーで盗んだチョコ1個。同級生たちと一緒にいじめた一人の少女。道端で懸命に餌を運んでいるアリを理由もなく踏み殺した、15歳のある日の夕暮れ。
父と母に守られ、きわめて恵まれた「やさしい世界」で育ってきたある思春期の少年は、卵から孵るひなのように「もうひとつの世界」を経験しなければならなかった。苦しみながら大きく成長しようとする少年の心の内をありありと描いた、ヘルマン・ヘッセの小説「デミアン」を数日かけて追っていきます。ーーー
ーヘッセ「デミアン」より。とある少年のお話ー
仲間どうしで「悪」を自慢しあう、というのが当時の僕たちの習慣だった。
ある日、いつもの橋げたの下に集まってきたのは、僕と、仲間の中で一番強い存在であり家柄も悪く体格のいいフランツ・クロオマア少年と、その取り巻きたちだった。

少年たちはめいめい自分の武勇伝を語った。とうとう僕の番になったが、僕は相変わらず弱虫だったので、語れるような「ワルイ」ことは何一つやらかしたことがなかったのである。
しかし何か言わなければ、僕は仲間にも入れてもらえないし、明日からは弱虫として大いに軽蔑されるだろう。
「俺は・・・、あの果樹園にあるリンゴの木から、リンゴの実を盗んでやったのさ。」
僕は自分の悪事をでっち上げた。
フランツ・クロオマア少年は、細めた目の中から、突き刺すように僕をじっと見つめた。そして、脅すような声でこう聞いた。
「それ、ほんとかい?」
いまさら引き下がることはできまい。僕は本当だ、と言い張った。
「じゃ、こう言うんだ。天地神明にちかって、とね。」
僕は軽々しく言った。「天地神明にちかって。」
だがその後、地獄が訪れた。
クロオマア少年は、帰り道、意気揚々と家路をたどっている僕の肩をつかんで呼び止めたのだった。
「なんだい。」
「なあ、坊や。あの果樹園が誰のものだか、俺が教えてやってもいいぞ。リンゴが盗まれているのを、俺はだいぶ前からもう知っている。そして、誰が果物を盗んだのか知らせることができるやつには、誰にでも二マルクやる、と主人が言っているのも、俺は知っているのさ。」
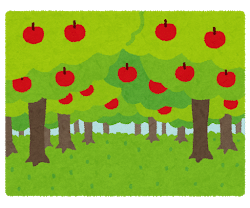
「まさか、君はあいつに何もいいやしないだろうね。」
すでに無駄だと感じていたが、一応、彼の心に訴えてみた。
「なんにもいわない?」クロオマアは笑った。「おい、お前、いったい君は俺が贋金づくりか何かで二マルクを作れるとでも思っているのかい。俺は貧乏人だ。俺には、お前みたいに金持ちの親父がいないのさ。だから二マルク稼げる時にゃ、稼がなきゃね。もしかしたら、もっと多いかもしれない。」
涙がこみあげてきた。もはや取り返しがつかない。
僕は自分の家へ帰り、上へのぼっていくことができなかった。僕の生活は破壊されてしまったのだ。僕は逃げ出すことを、そして二度と再び帰ってこないか、または身投げをすることを考えた。(中略)僕は放蕩息子が、昔ながらのふるさとの部屋の、ながめやにおいを迎えるようにそれらすべてを哀願しながら、感謝しながらむかえたのである。しかしそれらすべては、もはや僕のものではなかった。それらすべては、明るい父の世界、母の世界なのに、僕は深く、やましい気持ちで見知らぬ流れの中へ沈み、冒険と罪悪に巻き込まれ、敵に脅かされ、危険と不安と汚辱に満ちている。(中略)何よりもまず感じたのは、自分の道が今やますます下り坂になって、やみの中へ突き進んでいく、という確かさであった。自分の過ちから、新しい過ちが生じてくるに違いないこと、自分が兄弟のところに姿を見せたり、両親に挨拶したり接吻したりするのは「いつわりだ」ということ、自分はある運命と秘密を持ち歩きながら、それを心の中にかくしている、ということを、僕は明らかに自覚していたのである。(ヘルマン・ヘッセ「デミアン」より)
だが、夕べになって、父がいつもと変わらない調子で僕にキスをしてくれた時、僕の中で妙に新しい感情がきらめいたのだった。それは、恐るべき感情だった。
僕は一瞬、父の無知に対して、一種の軽蔑を感じたのである。父の冗談や、笑い声が僕にはくだらなく思えた。まるで自分が殺人を告白すべきなのに、巻きパン一つ盗んだことで尋問されている、そういう犯罪者になったような気がしたのだ。
(続く)
ー解説ー
「大人になる」ってどういうことなんだろう?
学校の先生や親たちは、自分たちの言うことをよく聞く子供を褒めたりします。
しかし、「大人たちの言うことをよく聞く」というのは、ほとんどの場合「何もしない」ということとほとんど同じ意味です。何もせず、ただ学校の勉強だけしてればいい・・・
小説の中の「僕」、つまり明るい世界の中で生きる、恵まれた気弱な少年は、その小さな心の中にある一つの疑問を育んでいきます。
そのように「大人たち」の言うことに対してただただ従順に生きていった結果、おれはどういう大人になるのだろう?
きっと、同じように子供に対して「正しいこと」のみを説いて憚らないような、そういう大人になるのだろう。
そして、彼は心の中に軽蔑を抱きます。
明るい世界の中でのうのうと手足を伸ばし、まるで自分自身がこの世の大正解であるような顔をして「正しさ」を説く、無知な大人たちを、思いっきり罵ってやりたくなるような、そんな感情。
しかし、彼は同時に気づいています。
そのような大人になることが、一番正しく、そして楽に生きる方法なのかもしれない。「正しい生き方」というものを否定して生きるのは非常に大きな危険が伴う。そして、何よりも孤独である。
少年はこれからどのように成長していくのでしょう。
これからも一緒に追っていきたいと思います。
漱石「夢十夜」より。孤独な時代への処方箋。
ーーー戦争。人間どうしが殺し合いをするなんて場面は、今生きている私たちにはとても考えられない。しかし、むしろ現代の日本の方が特殊なのではないか。有史以来戦争や争いごとが絶えたことはない。明日も生きていられる保証がある時なんて、一秒たりとも存在しなかったはず。
だとしても、その中で生きていた人々は皆、どうしようもないくらい残虐で思いやりがなかったのだろうか。そんなはずはない。彼らは果たして何を感じて生きていたのだろう。どういう絆で結ばれていたのだろう。
「夢十夜 第九夜」より
周りを見てみると、どうも侍の時代の話らしい。世の中がなんとなくざわつき始めている。今にも戦がおこりそうだ。それでいて、我が家の中はしんとして静かである。
家には若い母と3つになる子どもがいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは、月の出ていない夜中であった。草鞋を履いて、頭巾を被って、勝手口から出ていった。
父はそれっきり帰ってこなかった。母は毎日三つになる子どもに「お父様は?」と聞いている。子どもは何とも言わなかった。しばらくしてから「あっち」と答えるようになった。母が「いつお帰り?」と聞いてもやはり「あっち」と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして、「今にお帰り」という言葉を何べんとなく繰り返して教えた。けれども子供は、「今に」だけを覚えたのみだった。
夜になって、あたりが静まると、母は短刀を腰に差して子供を背中に背負ってそっと出ていく。母はいつまでも草履を履いていた。子どもはこの草履をの音を聞きながら、母の背中で安心して眠ってしまうことがあった。
だらだらとした長い坂を下ると、古い神社があった。社殿には八幡宮という額がかかっている。
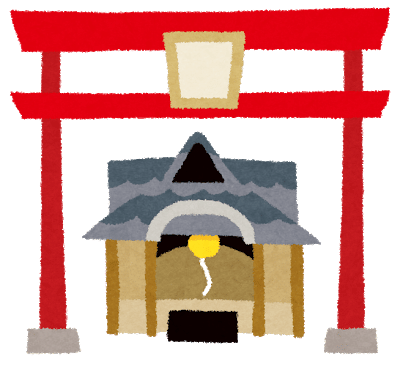
鳥居をくぐると杉の梢でいつもフクロウが鳴いている。そして、夜の神社の闇の中から、冷飯草履の音がぴちゃぴちゃした後、鈴が鳴らされ、柏手の音がする。たいていはこの時、フクロウは急に鳴かなくなる。それから母は、一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神さまのもとへ、こうやってしっかりと願をかけたら、よもや聞かれぬことはないだろうと一途に思いつめている。
子どもは急に泣き出すことがよくある。その時母は口の中で何かを祈りながら、背中を振ってあやそうとする。するとうまく泣き止むこともある。また、ますますはげしく泣きたてることもある。いずれにしても母は容易には帰らない。
一通り夫の身の上を祈ってしまうと、母は子供を欄干のそばにおろして、「いい子だから、少しの間、待っておいでよ」ときっと自分の頬を子供にすりつける。それから段々を降りてきて、二十間の敷石を行ったり来たりしてお百度を踏む。
子どもは暗闇の中で神社の境内の上を這いまわっている。そういう時は母にとってはなはだ楽な夜である。けれども縛った子にひいひい泣かれると、母は気が気でない。お百度を踏む足が速くなる。息が切れる。
こういう風に、幾晩となく母が気をもんで、夜も眠らずに心配していたとうの父は、とうに流浪の武士によって殺されていたのである。
こんな悲しい話を、夢の中で母から聞いた。
「孤独」と「争乱」は表裏一体
先日も記事を書いた、アランの「幸福論」を読み終わったとき、次のような言葉がとても印象に残ったのを今でも憶えています。
「戦争の中でこそ、真の美しい思いやりや絆が存在する。」
世の中が残虐で、夫も妻も子供でさえも、明日も生きていられる保証はまったくない、という時代。
そんな時代に生きるということは、いったいどういうことだったのでしょう。
私たちは運良くもそういう時代に生まれてこなかった。だから、その時代の人々が感じていたことを容易に想像することはできません。
しかし、もし目の前の相手も自分も、「明日本当に死ぬかもしれない。次の瞬間生きている保証はない。」というような世界に生きているとしたら。

想像してみましょう。
周りの人々への態度が変わってくるような気がしてきませんか。
見ず知らずの人間に対する警戒心はめちゃくちゃに強くなるでしょう。そう簡単に自分の目の前に現れた人間を信用しなくなるでしょう。当たり前です。もし騙されたら、命を奪われたり暴力を受けたり、取り返しのつかないことになる危険性があるわけです。
しかし、その一方で、長年連れ添っているようなかかわりの深い人をものすごく大切にするのではないでしょうか。
なぜなら、そういう絆の強い関係性は貴重だからです。誰がいつ死んでもおかしくない。誰がいつだれかに騙されてもおかしくない。そういう残酷な世で生きていくとしたら、少数の信用できる人間同士で強いきずなを結んで、その中で助け合って生きていくしかないからです。
私たちは、戦争のこととなると何でもかんでも否定しがちですし、実際戦争や争いごとは愚かで避けるべきことなのは間違いないですが、その真っ最中で生きていた人々が、仲間同士で築き合っていた絆や思いやりについては、もしかしたら現代のそれよりも深く優しいモノだったのかもしれない、と考えるのは間違っているでしょうか。
漱石の見た夢の中で、「母」は夫のために夜も寝ないでお百度を踏みます。現代ではとっても考えられません。結婚した夫婦の1/3が離婚するような昨今です。
きっと、当時はそれほど母にとって夫は貴重な存在だったのです。自分も子供も明日死ぬかもわからない様な世界の中で、本当に信頼できる人だったのです。
現代の妻にとっては、もし目の前の夫がいなくなったとしても、いくらでも魅力的な「代わり」がいるという確信があるのかもしれません。(夫についても同じです。)だからこそ、今目の前にいる人をとても大切に思う、という感情が失われつつあるのではないかという気がします。
世の中が平和であればあるほど、孤独な人は増えていくのかもしれません。
漱石「夢十夜」より。自殺の強い誘惑と後悔。
ーーー自殺を選んだ方は、死ぬ間際に何を思うのだろう。目の前に電車の車輪が迫ったとき。高層ビルの屋上から空を飛んでいる真っ最中。車の中で体が動かなくなり、意識が消えようとしている、まさにその瞬間。
ああ、これでやっと死ねる・・
もし喜びの感情を抱いて死へと歩んでいけたのならば、彼らの下した選択は正しかったのだろうか。
だが、もし、もはや死ぬしかないような、取り返しのつかない状況になったとき、「後悔」が胸を襲ってきたとしたら?
夏目漱石「夢十夜 第七夜」から、とある生きづらい男の話。ーーー

大きな船に乗っていた。
この船は毎日毎晩、すこしも止まることなく黒い煙を吐いて波を切って進んでいく。すさまじい音がした。
波の底から太陽が出る。それが高い帆柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して、先へいってしまう。太陽は船の進んでいく方向に沈む。
ある時自分は船の男を捕まえて聞いてみた。
「この船は西へ行くんですか。」
男はからからと笑った。
「西へ行く日の果ては東か。それはほんまか。東出る日のお里は西か。それもほんまか。身は波の上。流せ流せ。」と囃し立てる。
自分は大変心細くなった。いつ陸へ上れることだろう。どこへ行くのだかも全く分からない。ただ、波を切って進んでいくことだけは確かである。こんな船にいるよりいっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。
乗合はたくさんいた。いろんな顔をしていた。空が曇って船が揺れた時、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。彼女の眼を拭くハンカチの色が白く見えた。この女を見た時、悲しいのは自分ばかりではないことに気づいた。
夜になった。甲板の上に出て一人で星を眺めていたら、誰かがそばによってきた。「天文学を知っているか。」と尋ねてきた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学など知る必要がない。黙っていた。
今度そいつは、「神を信じるか」と尋ねてきた。自分はやはり黙っていた。
ある時食堂に入ってみると、派手な衣装を着た若い女が一心不乱にピアノを弾いていた。その傍に背の高い立派な男が立って、唱歌をうたっている。彼らは彼ら以外のことにはまるっきり頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ忘れているようだった。
自分はますますつまらなくなった。とうとう死ぬことに決心した。
そして、思い切って海の中に飛び込んだ。ところが、自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその瞬間に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は否が応でも海の中へ入らなければならない。
船は全く変わりなく、いつもの通り黒い煙を吐いて通り過ぎていった。自分はどこへ行くんだか分からない船でも、やっぱり乗っている方が良かったと初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖を抱いて黒い波の方へ静かに落ちていった。

今回の夏目漱石の第七夜、いかがだったでしょうか。
このお話が自殺の誘惑と後悔を描いたものであることは明白だと思います。
自分は「人生」という黒い大きな船に乗っている。その船はいったいどこに進んでいるのやらさっぱり分からない。明確な目的地さえ示されておらず、いつ自分が船を降りるのかさえも分からない。とにかく不安で仕方がない。耐え切れない。もう死んでしまおうか、とさえ思う。
周りを見てみれば、確かに自分と同じ時間を生きている人間は数多く存在するが、めいめい自分のことに夢中になって過ごしており、誰も「この船はどこへ行くのか」なんてナンセンスなことを考えているやつはいない。
「宇宙はいったいどうなっているのか」とか、「神を信じるか」とか、そういう問いで心をいっぱいにすることで「人生」の所在なさから目をそらしている人間もいる。
食堂でピアノを弾く若い男女のように、自分たちの人生の悦びを味わうのに夢中で、余計なことを考える暇もなさそうな連中もいる。
そうした「人生を生き生きと過ごすことができる人々」が、漱石には羨ましくて仕方がなかったのでしょう。
彼はともすると「自分はどうして生きるんだ?」とか、「生きることに意味はあるのか?」とか、いわゆる考えてもどうしようもないことを考えてしまうような気の毒な性格をしていたのでしょう。
そのようなことを考えてしまうと、人生が退屈で仕方が無くなってしまいます。彼は自殺の強い誘惑にかられ、それを実行してしまいます。
すると、まさしく「死」が決定づけられたその瞬間に、彼は急激に後悔の念に駆られます。自分はやっぱり生きていた方が良かった、しかしもう遅い。もう死ぬしかない。
最後の最後まで救いはなかったのです。自殺によって彼は救われず、むしろ後悔の念に溺れながら死んでゆくことになった。
多くの方が自殺している昨今。
自ら死を選ぶ、ということは大変痛ましいことです。しかし、彼らがいまわの際に考えることが、このような絶望的な感情だったとしたら。
漱石先生はこう言いたかったのでしょう。
俺と似たような性格をしている、生きづらい気の毒な方々は、自殺などしようと考えずに最後までしがみついてでも生きてほしい。どんなに惨めでも、どんなに人に迷惑をかけてもいい。もはや取り返しのつかなくなった状況で「やっぱり死ななきゃよかった」と思うよりは。
遅読のススメ
読書。その習慣の意味するところは人によってそれぞれです。
多くの場合、何かを学ぶために人は本を読みます。
巷には多くの本が出回っています。現代では特に、インターネットの隆盛によって紙の本が売れなくなっています。出版社も生き残りをかけて必死にマーケティングを行っています。

社会の競争は激化し、全体に「ゆとり」が無くなってきました。若者たちは特に恐怖に駆られています。とにかくお金を稼がないといけない。さもなければ、「負け組」と分類され、そのまま年を取り、たった一人で死んでいく。これが珍しいことでもなんでもなくなってきた。私自身も、自分で思っているより大きくこの恐怖感に捕らわれています。
金持ちになりたい。港区のタワーマンションに住みたい。ジャガーに乗りたい。何よりも、モテたい。
すべて人として当たり前の欲求です。
そのためには、情報があふれんばかりに氾濫するこの時代に、なるべく多くの情報を短時間で取り込むことができればできるほどコストパフォーマンスが良い。一日に何冊も本を読み、その内容をすべてインプットできる能力があれば、メンタリストDaiGoさんのような成功を夢見ることができるかもしれない。
そのために、「速読」の能力が必要だ。
たしかに。納得です。
しかし、ちょっと待ってほしいのです。あくせく考えて前に進もうとするのではなく、いったん立ち止まって考えてほしいのです。
はたして、これだけ多くの情報を「消費」した暁には、いったい何が残るのだろう??
毎日のように、超早いスピードで何冊も本を読みます。多くの情報が手に入り、知識も豊富になります。しかし、物事は必ず表裏一体で、メリットもデメリットもあります。「素早く文章を読む」ことのデメリットは何か?
それは、文章の細部に宿る美しさに気づかないまま読了してしまうことです。
本を読んだ後、「要約すると、全体的にこんな話だったよね」と誰かに語ることが出来さえすればいい、と思っているのなら、むちゃくちゃにもったいない話だなと僕は思います。
うまく伝わらないかもしれませんが、作家たちの書いた文章って、とてつもなく美しいものなんです。彼らが指先に血をにじませて書いた魂の一字一句を、マックのフライドポテトみたいに胃袋に流し込んでしまうのはあまりにも勿体ない。
じゃあ「美しい文章」って何なんだよ?
例えば、下のような文章です。
ウクライナの夜を知っておいでぢゃろうか。どうして、ウクライナの夜はご存じあるまい!さア御覧なされ!月は仲天から眺めおろし、広大無辺な蒼穹はいやが上にも果てしなく押し広がるように展開して、輝き、息づいてをる。下界はくまなく白銀の光にあふれ、妙なる空気はさわやかに息苦しく、甘いものうさを孕んで、薫香の大洋をゆすぶっている。神々しき夜だ!蠱惑的な夜だ!闇にとざされた森はさゆらぎもなく霊化したもののようにたたずみながら、厖大な陰影を落としてをる。また、かの池や沼は音もなく静まり返り、その水面の冷気と闇は暗緑の園によって邪険に区切られてをる。実桜と桜桃の樹のおぼこらしい叢林は、その根をおづおづと冷たい泉の中へ伸ばしているが、時々葉擦れの音を立ててざわめくのは、夜風といふ浮気男がちょいちょい忍び寄って接吻するのに腹を立てるのでもあろうか。見渡す限り地上のすべてがまどろんでいる。けれども天空は息づいてをる。ものみなが不可思議で、荘厳である。(ニコライ・ゴーゴリ作 平井肇訳 「ディカーニカ近郷夜話」より)
どうでしょうか。
作家ゴーゴリと訳者の平井肇氏が、文章の隅々まで、句読点に至るまで吟味に吟味を重ね、練り上げられた一つの芸術品として私たちの眼の中に飛び込んでくる、この贅沢で美麗な言葉の数々。
一字一句を読み落とさないよう、注意深く目をこらし、噛みしめながら読んでいきたくなるような、そんな名文もたくさんあります。
食事に喩えてみましょう。ファーストフードやカップラーメンなら、味も何も顧みず胃袋に流し込んでしまってもいいでしょう。しかし、フルコースのフランス料理を牛飲馬食で流し込んでしまうのはあまりにも勿体ない。このような感覚には同意していただけるでしょうか。
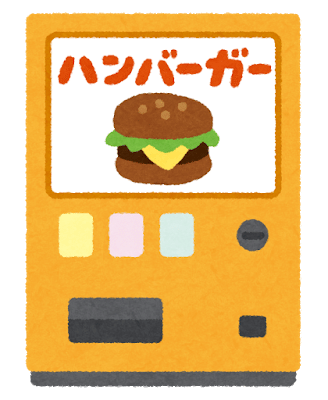
フルコースのフランス料理を流し込むのは、なぜもったいないのか。
「ファーストフードやカップラーメン」よりもはるかにお金がかかっているから。これが一番大きな理由でしょう。
しかし、文章の場合は話が違ってきます。さっきのような美しい作品がブックオフで百円で手に入ったり、はたまたKindleにて無料で読めちゃったりします。お金がかからないものには価値がない、という感覚に毒されてしまうと、これらの文章もすべて「短時間でなるべくコスパよく消費すべきもの」になってしまうのも分かります。
でも、僕は断乎として言います。
低コストでいろんな文学にアクセスできるそんな時こそ、一つの作品をじっくりと一字一句味わうような機会を持って欲しい。
読んだ文章を忘れてしまってもいい。どんなあらすじだったのか、どんなお話だったのかを忘れてしまっても構わない。しかし、泥水の底に溜まった一握の砂金のように、一生自分の中に輝き、残り続けるような一塊を手に入れることができるような、そんな読書をしてほしい。
多くの方は仕事をして生きなければなりませんし、毎日時間に追われている方もたくさんいらっしゃると思います。何年かかってもいいのです。一つの文学作品をゆっくり、じっくり噛みしめて読む、という体験を一度はしてほしいな、と願っております。
生き残りをかけた出版社たちの、「速読をすすめてなるべく多くの本を買わせる」という販売戦略にひっかからずに文章を味わう体験が、そこらじゅうに情報が氾濫している現代だからこそ絶対に必要です。
このような体験はとっても贅沢なものだと思いますし、一人の未熟な若者の世間知らずな主張だと言われても仕方がない、と思います。それでも一人でも多くの方に、文章が本来持っている感動的な美しさに目を向けていただけることを願って、これからも投稿し続けたいと思います。
「感受性」なんぞ、はたしていいモノなんだろうか?
私のブログでは、古来の芸術家たちが血を滴らせて書いた至高の文学を皆様にご紹介することを目的にしております。
得をするため、勝つために自分のすべてのエネルギーを捧げるのではなく、目の前に広がる世界の様々なものに関心を持つこと、冊子の中にある小さな世界にも感動できる感受性を思い出すこと。
大人になってから笑いものにしてきた、道ばたに咲く花の美しさ、実家近くの用水路に住んでいる魚たちの顔つき。
そんな、ほんのちょっとした美しさに気づくこと。
自己紹介noteでも申しあげたとおり、激しい競争社会から半分だけ降りて、日常の中に潜む様々な美しさに気づく感受性を少しでも思い出して生きていくことができればどんなに素敵だろう、と思っております。
しかし、そのような生き方には、少なからず不幸の影がつきまとうのではないか、と最近思い始めています。
日本の小説家の中で最も有名な芥川龍之介もまた、そのような人間のうちの一人だったに違いありません。
人生を幸福にするためには、日常の些事を愛さなければならぬ。雲の光、竹のそよぎ、群雀の声、行人の顔ーーあらゆる日常の些事のうちに無上の甘露味を感じなければならぬ。しかし、人生を幸福にするためには?ーーしかし些事を愛するものは些事のために苦しまなければならぬ。古池に飛びこんだ蛙は百年の愁いを破ったであろう。が、古池を飛び出した蛙は百年の愁いを与えたかもしれない。いや、芭蕉の一生は享楽の一生であると同時に、誰の目にもみて受苦の一生である。我々も微妙に楽しむためには、やはりまた微妙に苦しまなければならぬ。ーーー人生を幸福にするためには、日常の些事に苦しまなければならぬ。雲の光、竹のそよぎ、群雀の声、行人の顔、あらゆる日常の些事の中に地獄の苦痛を感じなければならぬ。(芥川龍之介 「侏儒の言葉」より
以上の芥川の言葉の通り、日常のほんのちょっとしたものを好きになれる感受性を持ち合わせているような方は、日常のほんのちょっとしたことにも悲しまなければならない運命を抱えているのではないか。
最近、そんなふうに思っております。
自分の外にあるモノにたいする感受性があまりにも強いため、他人の顔色がちょっと変わっただけでもすぐに気づいてしまって申し訳なく思ってしまったり、目の前でこっぴどく叱られている人に感情移入してしまったり、またはちょっと目を向ければそこら中に転がっているような、道を行く人々の苦しみや悲しみの影をあっという間に感じ取ってしまったり。
しかし。
おそらく多くの方が感じられていると思いますが、この世は頭が良くて鈍感であればあるほどうまくいきます。
あらゆる社交は、少なからず暴力の匂いを含んでいます。ビジネスの場では特にそうではないでしょうか。営業や商売の場面でも、目の前の人間が何を考えているのかを考える能力は大切です。しかし、それは「いかに相手を自分の意に沿わせるか」「いかに相手を騙して商品を買わせるか」という目的を軸としたスキルに終始しています。
つまり、あらゆる社会的な関わりをうまくやるためには、少なからず「マインドコントロール」の才能が必要だ、ということです。
これには、まず第一に非常に頭がよく切れる必要があります。そして、とことんまで「鈍感」であること。つまり、自分の目的を果たした結果、相手がどのような不利益を被るか、相手は何を思うのだろうか、なんてことは露ほどにも考えないような悪党にならなければなりません。
いわゆる敏感な方は、これがどうしてもできないのだと思います。だから、自分の苦手なものでも一生懸命やっているつもりなのに、全く結果が出ず、苦しみながら生きている。
私もまた、社会的な関わりをうまくやれないような不器用な人間のうちの一人です。文学たちの優しさに依存しながら生きているような人間です。いや、「自分はうまくやれない」とか何とか言って、社会の中で戦うことから逃げているだけかもしれませんが。
競争社会から「半分」降りる、と書きましたが、やっぱり社会から完全に降りるわけにもいきません。そしたらもう生きていけなくなっちゃいます。苦しくても完全にドロップアウトするわけにはいきません。助けてくれるかどうかも分からないような「芸術」だの「文学」にすがりつきながら、なんとかうまくやれるように自分の生き方を模索していくしかないでしょう。
私は今後もこのブログも続けます。これからも文学に依存して生きていきます。しかし、言い出しっぺのくせに誠に僭越ながら、「文学」だの「芸術」だのにあまり期待しない方がいい、とも思っております。文学なんぞ読みたい人だけが読めばいいのですし、芸術はそもそも、どこに行くのかもわからない、惨めな道のうちの一つなのですから。



